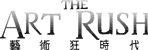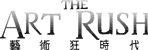|
 |
| ■フォト・アートの誕生「マン・レイ写真展」 |
No.005 |
| [場所] 美術館「えき」KYOTO |
| [期間] PART I 2003年6月4日(水)〜15日(日)、PART
II 6月17日(火)〜29日(日) |
| [料金] 800円(一般) |

【PART I】
6月8日(日)、実に1ヶ月ぶりくらいに足を運んだ展覧会は、ダダの芸術家マン・レイの写真展。500点を越す写真を2回の会期に分けて展示するというもので、もちろん通しのチケットを購入したよ。
ところで、マン・レイと言えば、写真家というよりは、芸術家というイメージが一般的かもしれないね。でもその割によく見かける代表作は写真ばかり・・・なぜ「写真家」ではなくて「芸術家」なのだろうと不思議に思う人もいるんじゃないかな。なにを隠そう、ボクもその一人なんだ。ここで今更「写真は藝術か」なんて分かりきった議論はしないけれど、なぜ彼だけが写真を撮る者として美術史に登場するのか・・・その辺りを探ってみようよ。
この写真展を見てまず驚くのは、現代の写真家に通じるイメージが多々あるということだね。藝術というよりもあまりに「写真ッポイ」んだ。
しかしこれは逆説的に、写真が藝術を飲み込んでしまったことの結果とも言えるんじゃないかな。つまり”今”見るから写真ッポク見えるってこと。もっと言えば制作当時、これらの写真は明らかに藝術だったということなんだ。
一方で、彼は「写真」も撮っていたんだ。それは日常的な記録や記念写真的なものなんだけど、その”自分と関係するものは何でも撮ってやろう”という姿勢は明らかに写真家のそれだよね。
プライベートでも記録を残し、コマーシャルフォトのような芸術的な商業イメージ作成の仕事もこなす。
こうして見ると、彼は現代の写真家と呼ばれる人達の原型と言えるんじゃないかな。
正直、この写真展では「未公開作品多数」と謳っていたから、どんな写真が出てくるのか不安もあったんだ。だって、いい作品はすでに世に出ていて、未公開作品と言えば質の悪いものばかりというパターンが多いのも事実だからね。
でも、今回はそんな未公開の写真群が、芸術家の写真家としての面を浮かび上がらせていたってこと。
これを書いている時点ではまだPART IIを見ていないんだけど、見るのが楽しみになったよ。
【PART II】
6月28日(土)、第二部を見てきたよ。前半に第一部と共通の展示もあったものの、後半は全て入れ替わっていたね。
内容は、 第一部が、実験的な写真や日常スナップ的な写真で構成されていたんだけど、第二部は仕事としてのファッション写真、風景写真等から構成されていたんだ。
ここでもマン・レイの“何でも写真に撮る”という姿勢はより明らかになったってワケだね。
でもね、それじゃなぜ彼は芸術家として美術史に出てくるのかってことだけど―――それは美術史の教科書とこの展覧会を実際に見比べてみれば分かると思うよ。
どういうことかと言うと、美術史の教科書に紹介されているマン・レイの写真作品は、彼の撮る中でもある特定のジャンルの写真に限られているってこと。
そしてもうひとつ、彼は確かに写真以外の藝術作品を残してもいるという事実がある。
これらのことから、彼の藝術として認知されている写真はほんの一部であって、それも彼が芸術家としての活動をしていたからこそ美術史に取り上げられている、とは考えられないかな。つまり、マン・レイという人物は、写真と藝術とが触れ合う接点だった、ということ。
彼は「写真は藝術ではない」なんて言っているのだけれど、その本当の意味は・・・もう分かるよね?
そう、写真は「藝術」なんていう狭い世界には全然収まりきらないってことさ。
|
| |
|
 |